いま家を買うべき?賃貸のままがいい?買うなら適正価格は?|カウルのお悩み相談室
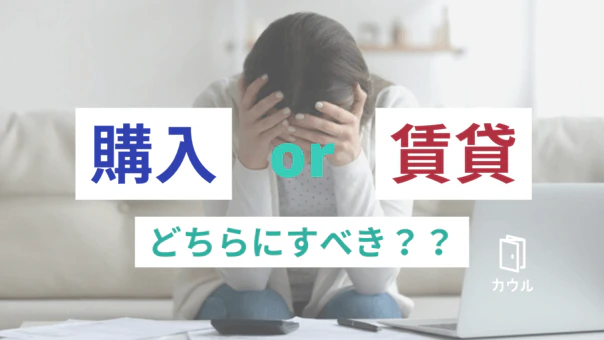
不動産購入にまつわるお悩みは複雑だからこそ、なかなか気軽に人に相談できないもの。
「カウルのお悩み相談室」は、カウルユーザーから届いたリアルなお悩みに、その道のプロがズバリ答える連載企画です。
今回は、賃貸から購入に切り替えるべきか、お悩み中の方からのご質問。今お住まいのエリアは中古マンションでも価格帯が高く、コスパの良いマンション選びに苦心しているご様子。購入するならいくらが適正なのか?・・とお悩み中です。果たして、プロの見解は?
お答えいただくのは、不動産運用にも強いファイナンシャルプランナー 森祐司さんです。
森 祐司

今回のご相談内容
Q:「購入したほうがよいのか、それとも賃貸のままのほうがよいのか。購入するならいくらが適正なのか?」
Aさん:
「購入したほうがよいのか、それとも賃貸のままのほうがよいのか悩んでいます。購入する場合、いつどのくらいの価格の家を買うのがよいでしょうか。
子どもが小学生なので、できるだけ今住んでいる場所で探していますが、坪単価が高いため中古マンションでも高額な物件しかありません。安心した住宅購入のためには、何よりリスクを減らすことが最優先だと思っています。コスパがよく、身の丈に合った物件を見つけたいと思い、物件や条件を探している段階です。
今のところ明確な夢や目標はありませんが、しいていえば家族のために家を購入したほうがよいのかを悩んでいます」
<<Aさんプロフィール>>
■現在のお住まい:賃貸
■ご年収(世帯年収):800~900万円未満
■家族形態:ファミリー(小学生のお子さん)
■今後大切にしていきたいこと(「家族との時間、仕事、交友関係、趣味、学び、経済力」の中から優先順位の高い順に3つ):
1位:経済力
2位:家族との時間
3位:学び(資格取得など)
回答:「◯◯◯◯◯◯◯を基準に判断しよう」
編集部:
「物件価格が高止まりしている現在、同じようなお悩みを抱えている方は多そうですね。果たして、どこを基準に判断すればよいのでしょうか?」
森さん:
「物件の適正な購入金額について、よく見かけるのは年収の〇倍、といった基準です。それも間違ってはいないものの、実際はご夫婦のどちらかがパート・時短になるなど、働き方が変わることで世帯年収が変わることもあるでしょう。どちらかというと世帯年収より、物件を買った後の年間貯蓄可能額が大切かと思います」
編集部:
「世帯年収ではなく、物件を買った後の年間貯蓄可能額ですか・・詳しくご説明いただけますか?」
森さん:
「物件を買った後、ローンや管理費修繕費、固定資産税を払ったあと、年間でどのくらいお金が貯められそうか、が重要です。教育費の貯蓄、老後資金、お仕事を引退された際に残りのローンを完済できる貯蓄などが十分できる家計であれば、多少高い物件でも購入の余地がありそうです」
編集部:
「ご相談者さんは、今は比較的高価格帯のエリアに賃貸でお住まいのようですね」
森さん:
「坪単価が高いエリアということは、恐らく資産価値があり、物件価格が下落しづらく、住宅ローン完済後に資産となっている可能性もあります。物件購入後に貯蓄が難しくなるようでしたら、予算は無理せず、築年数などの条件を緩和するのはいかがでしょうか」
編集部:
「賃貸がいいのか、買った方がいいのか、ともおっしゃっていますが、賃貸で住み続けることに関してはどう考えるのがよいでしょうか?」
森さん:
「例えば賃貸なら家賃補助10万円/月、購入後は1万円/月、などお勤め先の住居費の補助が購入か賃貸で全く異なる場合は、その期間は賃貸のほうが良いかも知れません。そうでない場合はやはり買ったほうが不動産で資産形成ができ、良いと考えます。
また、買ったほうが良い理由のもうひとつとしては、日本は住宅ローンが諸外国と比較して低金利なので、賃貸の10万円と、住宅ローン返済10万円を比較した時に、購入のほうがグレードが高いところに住める可能性が高い、というのも挙げられます」
今回のお悩み・回答まとめ
- 年間貯蓄可能額=物件を購入した後に、年間でどのくらい貯蓄ができそうか、を基準に判断しよう
- 物件購入後に貯蓄が難しくなるようであれば予算は無理せず、築年数などの条件を緩和してはどうか
- お勤め先の住居費の補助の影響がなければ、賃貸よりも購入がおすすめ
今回は、物件を買うべきか、買うのであればいくらくらいの価格のものがいいのか、というご相談でした。
簡単なライフプランシミュレーションは、金融庁をはじめ全国銀行協会、金融広報中央委員会、日本FP協会など、各団体が無料診断ツールをネットで公開しています(「ライフプランシミュレーション」で検索すると多数見つかります)。ひとつの基準として、活用してみるとよいでしょう。
将来的に必要な貯蓄額や具体的な物件価格など、いつどのくらいのお金が必要で今どうすればいいかを描いた詳細なシミュレーションやキャッシュフロー表、具体的なアドバイスが必要な方は、ファイナンシャルプランナーに一度相談されてみるのもよいでしょう。%20(604%20%C3%97%20150%20px)%20(4)%20(1).png?w=604&h=150)
FPに聞いてみた。FPってどこまで相談できるの?なぜ相談が無料なの?
住宅購入や資産運用、家計管理など暮らしにまつわるお金について検索すれば、必ずといっていいほど出てくる「ファイナンシャルプランナー(FP)」。
「FPって、よく無料の相談窓口を見かけるけれど、強く営業されたり金融商品を売られるのでは・・?」
「聞いてもらいたい悩みはあるけれど、どこまで相談できるの?」など、興味はあるけれどよくわからない、という方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで、FPに向いている人や利用のコツ、なぜ無料なのか等々、森さんにズバリ聞いてみました。
FPへの相談、どんな人が向いている?
編集部:
「Ever Sideさんのホームページでは、FPについて『お客さまのマネープランの計画と実行をお手伝いするお金の相談相手』とおっしゃられています。一口に『暮らしのお金の相談』といっても、一体どこからどこまで相談していいのでしょう? どんな方が向いていますか?」
森さん:
「まず、FPへの相談が合っている方は、何より『お悩みを抱える人』です。具体的には、こんな方がお客様には多いですね。
- 時間がなく1つの窓口に、お金まわりの相談をすべてお任せしたい方
- セカンドオピニオンが欲しい方(不動産業者に〇千万円の住宅を提案されているが、価格が適正か診断してほしい、など)
- 悩み事が複合的な方(家と家計管理、保険、投資、税金など複数の要素が絡んでいる)
- ライフプランを一緒に考えて欲しい方
反対に、あまりおすすめしないのはこんな方です。
- ネットや書籍でご自分で情報をかなり調べており、それらに対してしっかり自信を持って自分でライフプランニングをしている方
こうした方はまずはご自分で立てたライフプランを実行されてみて、その過程で適宜修正されていくのがよろしいのではないかと思います」
FPへ相談する時のコツってあるの?
編集部:
「なるほど、相談できるだけの具体的な準備が必要なのかと思っていたのですが、逆に整理されていない状態でいいんですね。では、実際にFPさんに相談する時の上手な相談方法や心構えみたいなものはありますか?」
森さん:
「私がご提案する際には、まずは相談内容をとにかくすべてお聞きします。とにかくしゃべっていただきます。その上で、入るお金、出るお金で何があるかをすべて聞きます。
そこで一旦私の方で持ち帰らせていただき、後日改めて課題、対策、取り組むべきことをご提案する、という流れです。
最初のご相談(※無料)では、『一番今日解決したい優先事項』を聞きますが、ケガに例えると、お客様が気付いていない場所から出血している、というケースもありえます。お話を聞くなかでそれがわかった場合は、そこの対処を最優先にすべき、など対処法をご提案させていただくので、まずはご安心してお話しいただければと思います。
また、弊社では初回相談は無料にしています。これは、まずはお互いのすり合わせを行う必要があるためです。相談者様側は「FPはこういうもの」という経験をし、FP側は相談内容に対応できるかを確認するための場が、初回相談なのです。相談金額を含めて双方で合意形成をとって初めて『ご依頼いただく』という形になりますので、ご安心ください。
住宅に限らずお金に関して何かモヤモヤを抱えていらっしゃる方は、まずはお気軽に初回相談を申し込んでみてください。流れについては、こちらのページで詳しく紹介しておりますので、合わせてご参考になさってください」
参考:ご相談の流れ(Ever Side株式会社)
マンションジャーナル編集部のまとめ:「まずは話すことで解決への道が開ける」
森さんに今回お話を伺うなかで、お金の悩みはまずは解体・整理して、見通しをよくすることが大事だと痛感しました。一人や身内だけでは、なかなかお金にまつわることを棚卸しすると言われても、考えるだけでシンドイもの・・。だからこそ、伴走者や指導役としてFPがいるのですね。
ファイナンシャルプランナー(FP)の初回相談が無料なのは、両者間で合意形成するためであるというのも納得です。もしお金に関して解決したい課題をお持ち方は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。%20(604%20%C3%97%20150%20px)%20(4)%20(1).png?w=604&h=150)
(PR)
マンションジャーナル編集部
「Housmart(ハウスマート)」が、購入や売却に必要な基礎知識・ノウハウ、資産価値の高い中古マンションの物件情報詳細、ディベロッパーや街などの不動産情報をお届けします。
.png?fm=webp&w=232)
%20(1).png?fm=webp&w=232)
